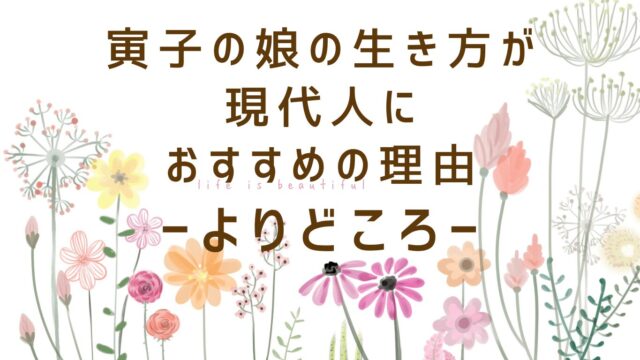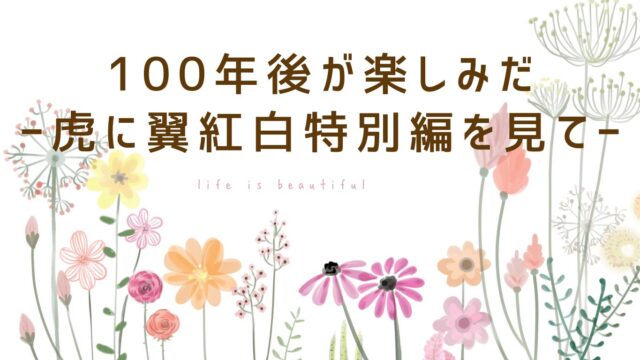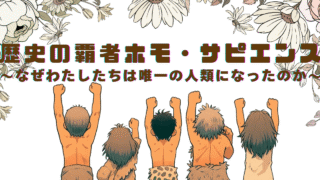日本国憲法制定時に尊属殺を残したのはなぜ?

はじめに
戦後に新しい憲法ができたとき、なぜ尊属殺重罰規定:「親を殺した場合の重い刑罰」は残されたのでしょうか。この疑問を考えるとき、明治時代から戦後にかけて、日本が「どうしても守りたかったもの」に注目すると、答えが見えてきます。
➔➔➔パレスチナ最後の石鹸工場を支援尊属殺とは
尊属殺とは、自分よりも前の世代の人、例えば父や母、祖父や祖母を殺してしまうことを指します。日本では昔から、親や祖父母を大切にすることが重要とされてきました。
尊属殺の刑法の歴史
1880年(明治13年)旧刑法 尊属殺は死刑
1908年(明治40年)新刑法 尊属殺は死刑or無期懲役 ←配偶者の尊属殺も加わる
1946年(昭和21年)日本国憲法公布
1947年(昭和22年)刑法改正 ←尊属殺重罰規定は存続
1950年(昭和25年)最高裁にて13対2で尊属殺重罰規定は合憲と判断
1973年(昭和48年)最高裁にて2対13で尊属殺重罰規定は違憲と判断
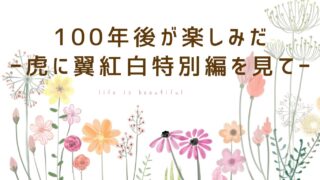
1995年(平成7年)刑法改正 ←尊属殺重罰規定削除
明治時代:外国に負けない国を作るための法律作り
「立派な国に見せる」ための法律
明治時代、日本は西洋の強い国々と対等に付き合うために、急いで近代的な法律を作りました。外国から専門家を招いて指導してもらい、表向きは西洋と同じような法制度を整えたのです。
しかし、これは単なる「見た目を整える作業」ではありませんでした。
天皇中心の国作りと武士の精神を法律に込める
日本が本当に目指していたのは、天皇を中心とした強い国を作ることでした。そして、武士が大切にしてきた精神—特に「忠義」と「孝行」—を、新しい法律の中にしっかりと組み込もうとしたのです。
「忠義」とは国や天皇への忠誠心、「孝行」とは親を大切にする心です。この二つを「忠孝両全」と呼び、日本人の理想とされました。
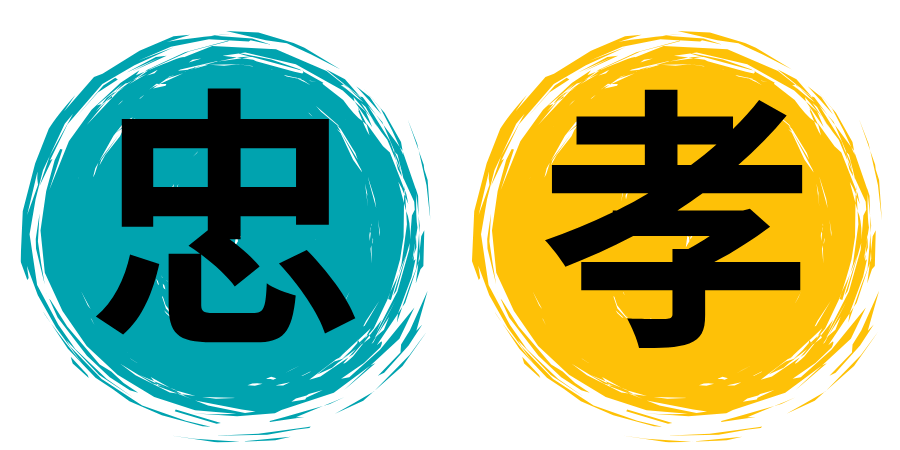
戦後:巧妙な「精神の守り方」
天皇への忠誠は諦め、親への孝行は守る
戦争に負けた日本は、アメリカ軍(GHQ)の指導で新しい憲法を作ることになりました。このとき、天皇への絶対的な忠誠心は完全に捨てることになりました。天皇は「神様」ではなく「象徴」になり、天皇を侮辱した罪(不敬罪)も法律から消えました。
しかし、日本側には強い思いがありました。「天皇への忠誠は諦めるしかないが、せめて親を大切にする心だけは法律で守り続けたい」—この思いが、親殺しの重罰を残す理由だったのではないでしょうか。
新憲法と矛盾するのを承知で残した
新しい憲法には「すべての人は法律の前で平等」と書かれています。でも親殺しだけ特別に重く罰するのは、明らかにこの平等原則に反します。
当時の人たちの中にもこの矛盾は指摘されていました。それでも親殺し重罰を残した理由は、「法律の筋を通すこと」よりも「親を敬う心を法律で守ること」の方が大事だと考える声のほうが大きかったのでしょう。
法律と道徳の関係が大きく変わった
昔:法律が人々の心を教育していた時代
明治時代から戦前まで、法律は単なるルールではありませんでした。「法律を通じて国民の道徳を作る」という考え方が主流だったのです。
これは簡単に言えば、お役人が庶民に対して「法律でこう決まっているから、これは悪いことなんですよ」と教える仕組みでした。法律が道徳の先生のような役割を果たしていたのです。
今:個人がそれぞれの価値観を持つ時代
現代の日本では、この関係は完全に変わりました。私たちはそれぞれ自分なりの考えや価値観を持っています。法律は守りますが、「法律に書いてあるから正しい」とは思いません。
法律は最低限のルールに過ぎず、何が正しいか、どう生きるべきかは、個人の経験や環境によって決まるようになったのです。
親子関係も人それぞれの時代に
昔の教えは知っているが、実践は自由
孔子の「親を大切にしなさい」という教えは、今でも多くの日本人が知っています。しかし、実際に親を敬うかどうかは、完全に個人の判断になりました。
どんな家庭で育ったか、親とどんな関係だったか、周りの親子をどう見てきたか—こうした個人的な体験によって、親への態度は決まります。「法律で決められているから親を敬う」という時代ではなくなったのです。
まとめ:時代遅れになった「心を守る法律」
尊属殺重罰規定が日本国憲法制定時に残された背景には、日本の大切にしていた考え方を守りたいという思いがあったのでしょう。しかし、社会の価値観が多様化し、法律のあり方が変わったともいえます。
1973年の最高裁判決で「違憲」とされ、1995年についに法律から消えたのは、日本社会が大きく成熟した証拠かもしれません。
法律は法律として、道徳は個人の選択として—この分離こそが、現代日本社会の成熟の証なのではないでしょうか。
最後まで読んでくださりありがとうございました!